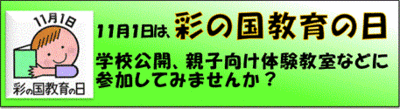R.7活動の様子
終業式の前日は・・・
1学期の最終日を前に、各学級では様々な活動を行っていました。
みんなで話し合って決めた集会活動「1学期がんばったね会」を行っているクラス、林間学校のキャンプファイヤーで仲を深めたレクリエーションを改めてクラス全員で取り組んでいるクラス、1学期に使ったげた箱をきれいに掃除しているクラス・・・。6年生は夏休み明けの修学旅行に向けた話し合いもしていました。子ども達が行っていたこのような【みんなで決めたことをみんなで行うこと】【きれいにすることで感謝の気持ちを表現すること】【今、自分たちがやるべきことを考え協働して活動すること】は、1学期の自分たちの成長を振り返ることができ、とても価値ある活動だと感じます。
 |
|
1年生の給食の様子を見ると、配膳・食事・片付けがとても手際よく、丁寧に行えるようになっていて驚きました。給食が始まって3か月。子ども達の成長・変化は大きくてよく行動に表れています。今日は特日課でしたので、調理員のみなさんもいつもより早く給食の準備を進めてくださいました。たくさん食べることや自分の言葉で感謝の気持ちを伝えられましたね!
硬筆展の表彰朝会でキラリ☆
今日は、5月~6月に取り組んだ硬筆展で【特選賞】に選ばれた児童への賞状伝達を行いました。名前を呼ばれると「はいっ!」と力強く返事をする6年生に引っ張られるように、どの学年でも体育館にはっきり聞こえる声で返事をする児童が多くみられました。みんなの前ではっきりと返事をしようとした姿が「キラリ」。たくさん練習をしたのでしょう。下級生の返事をよりよりものに引き上げた6年生の姿も「キラリ」輝いていました。
また、所沢市の代表に選出された4年生の児童がステージで賞状を受け取りました。みんなの視線を集める中、堂々とした態度で受け取ると大きな拍手がありました(キラリ)。立っている児童にも大きな拍手があり、頑張った子を認め合うあたたかな気持ちが伝わってきました。友達や自分のがんばりを認める姿も「キラリ」☆彡です。
夏休みには、自分で内容を決めて取り組む課題もありますので、自分の創意工夫を生かして頑張ってほしいと思います。
中富小の田んぼで稲が
今年、亀池から田んぼに作り替えていただいた場所に5年生が田植えをした苗が
すくすくと育っています。
毎日、天気予報も気にしながら、水の量を気にしながら、田んぼをながめている子供たちが
たくさんいます。
今日も風になびかれた稲が気持ちよさそうにそよいでいます。
学校に来たら田んぼやビオトープの変化に目を向けてみてください。
学校応援団「見守り」のみなさん☆彡キラリ
1学期もあとわずかとなりました。
「安全・安心な学校」これは当たり前でなければならないことですが、
それを維持し続けることは簡単なことではありません。
それには多くの人たちの温かな思いや思いから生まれた行為によって
支えられています。
その大きな原動力の一つが、学校応援団「見守り」のみなさんのキラリ輝く思いと思いに基づく取り組みです。
今、地域全体で子供たちが安全に通える学校づくりに協力してくださる方々が
増えています。
何もしないで安全な場所や安心な場所をつくることはできません。
一人一人が何ができるか、一人一人のキラリをあわせて
大きな輝きで安全・安心な街をつくっていきましょう!
学校応援団「読み聞かせ」のみなさん☆彡キラリ
月曜日は読み聞かせの日です。
今日は1学期最後の「読み聞かせ」の時間となりました。
1学期の初めに比べて「読み聞かせ」の学校応援団の方々の数も増えてきています。
体験・見学の方もお越しになっています。
読み聞かせの時間は、子どもたちが豊かな心を育み、未来に向けて大きく羽ばたくための大切な時間となっています。
一人で聴くだけでなく、みんなで聴くといろいろな反応もあって、それが楽しさを膨らませてくれてもいます。
学校応援団「読み聞かせ」の方々は、今日はどんな本を読もうか、どんな反応があるかなどいろいろ考えて本を選んできてくださっています。
そんな方々の思いもきっと伝わって、たくさんのキラリがあふれる時間となっているように思います。
読み聞かせが終わった後に、打ち合わせをしていたみなさんに、5・6組の子供たちが
今日取れた朝どれ野菜の販売を行いました。
毎日のようにたくさんの人が学校を訪れ、その中でコミュニケーションがかわされ、
人的な化学変化が起こり、新たな学習の機会が増えつつあります。
また、新たな学びだけでなく、学校が整備されたきれいな公園のようになっていき、
学校が子供たちにとってこれまで以上に安全で、安心な場となりつつあります。
学校に来るだけでも、そういった学校づくりに貢献できます。
そして、来校された方々にも新たな学びの場、憩いの場となることを願っています。
1年生:外来種「アメリカセンダングサ」をとりのぞこう!
5時間も大変暑い日になりました。
授業の初めに、メダカの放流も行いました。
「アメリカセンダングサ」は、北アメリカが原産国となっています。
とても繁殖力が強いため、他の植物の生育を妨げてしまいます。中富小のビオトープにもたくさん生えてしまっています。
そこで、今日は、1年生が持続可能な環境づくりの学習で外来種「アメリカセンダングサ」をビオトープから取り除く学習を行いました。写真のように「アメリカセンダングサ」が入ったファイルを見ながら、その草を探して抜く作業を進めました。
みんな、国語の「大きなカブ」の学習をしたこともあり、大きなアメリカセンダングサを一生懸命抜くことをがんばりました。
みんなで暑さを忘れるほど、大きな草と奮闘しました。
お手伝いに来て下った学校応援団、保護者の方々のご協力もあり、本当によくがんばりました。
日本には大正時代にやってきたと考えられ、今は日本全国でふつうに見られる存在になっています。水田や湿地などの水辺を好みますが、環境適応能力が強いため、畑地や乾燥した荒れ地などにも生えることがあります。
アメリカセンダングサのタネは、洋服や動物の体にくっついて遠くまで運ばれていく「ひっつき虫」とも呼ばれています。
タネの先に2本の長い刺があり、これで突き刺さるように引っかかる仕組みになっています。
その刺には、すぐにすとんと抜けてしまわないように、「すべり止め」となる逆向きの小さな刺が生えています。
ただ洋服の場合、これが仇になって、がっしり刺さったまま取れなくなってしまうことが多いようですが。
運動場排水施設の本格再稼働に向けて
昨年度より長年稼働していなかった運動場の排水施設の再稼働に向けて工事を進めてきてもらっています。
溜まった水を強制的に排水するポンプは現在、修理は完了しており、排水ができているかを確認中です。
また、運動場の周りにある排水溝の一部にまだ土が積もっているためにそれを取り除く工事を進めてもらっています。
暑い中、作業をしてくださっている方々に感謝です。
5.6組で販売学習を実施しました
1学期末に行われた授業参観、懇談会に合わせて、5、6組ではこれまで育ててきた野菜を保護者の方々に向けて販売する学習を昼休みの時間帯に実施しました。
販売学習は、単に野菜を売るという活動に留まらず、子どもたちが社会の中で自立して生きていくために必要な「生きる力」を総合的に育むための非常に有効な教育活動です。
お金の数え方、商品の値段設定、お釣りの計算など、具体的な場面を通して金銭感覚を養います。
お客様とのやり取り(「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」「いくらです」など)を通して、挨拶や敬語、丁寧な言葉遣いを学び、状況に応じた会話の練習ともなります。
商品の陳列、袋詰め、レジ打ちなど、それぞれが役割を分担し、協力して一つの目標を達成する経験を積みこともできます。
労働の対価としてお金を得る喜びや、お客様に感謝される喜びを体験することで、「働くこと」への前向きな意識を育みます。
自分たちが種から育てた野菜が商品となり、お客様に喜んで買ってもらえる経験は、大きな達成感と自信につながります。子どもたちにとって、具体的な成果が見える活動は自己肯定感を高める上で非常に効果的です。
自分の作ったものが人の役に立つ、喜ばれるという経験を通じて、「自分にもできること」や「自分は役に立つ存在である」という自己有用感も育みます。
成功体験を積み重ね、自己肯定感を高めながら、将来の社会参加に向けた基盤を築く上で、今回の取組は大きな意義があると言えるでしょう。たくさんのキラリが見えました。
多くの保護者の方々にご協力いただきました。ありがとうございました。
7/4 本校で北地区幼児教育振興協議会を開催しました
7月4日(金)に、本校を会場として北地区幼児教育振興協議会が実施されました。
開催にあたっては、1年1組の算数の授業を公開しました。
参会者の幼稚園、保育園、小学校、どの先生方からも、賞賛の言葉をいただきました。
この時期の1年生が5時間目にも関わらず授業に集中してよく取り組んでいること、聴く姿勢やノートの取り方、字を書く量などどこもよくできていることについて話が出ました。
卒園した園児がいる幼稚園、保育園も多かったこともあり、「入学する前は~だったのに」と子供たちの成長を喜んでおられる方が多くおりました。
小学1 年生の算数で学ぶ引き算の種類は、大きく分けて「求残」「求差」「求補」の 3 つがあります。今回は、これまで行ってきた「求残」いわゆる「残りは?」ではなく、「求差」・「ちがいは?」という問題で、子供たちにとっては、その意味理解が難しい学習です。
さらに、参会者の方からは、担任の先生の丁寧な授業の進め方や児童に対する教師発話(非言語的なコミュニケーション【ジェスチャー、表情 、視線など】も含む)について意見がよく出ました。
先生の話し方、間の取り方、子供の言葉への返し方、特に、写真のような表情がとてもおだやかでよかった、という意見が多く出されました。その後、協議会の中では、幼・保・小の滑らかな接続について話が出ました。
朝、学校に来ると…
毎日、田んぼの様子が気になります。
特に、月曜日の朝は。時々、天気が悪いと休みの日にも見に来ることも。
みなさんにも、そんなことはないですか?
今日学校に来ると、田んぼの苗が生き生きとしています。
なんだかいつもより少し変な感じが…
日曜日に、PTA会長さんが稲の苗をさらに植えてくれていたのです。
本当にありがたいです。
休みの日、学校に来たら野菜や植物、ビオトープの整備にお力をお貸しください。
みんなで持続可能な環境を中富小につくっていきましょう。